2025/06/24
「夜中に足がつる」その理由と対処法と⁉︎
こんにちは😃
ご覧いただきまして、ありがとうございます♪
◎【水分不足?姿勢の問題?それとも別のサインかも?】
「イタタッ!」と夜中に飛び起きるあの痛み…
最近「夜中に足がつって飛び起きて、つい首まで寝違えてしまった…」という患者様がご来院されました。実は、この「こむら返り」ただの水分不足ではなく、日ごろの姿勢の悪さや骨盤の歪みが関係していることが多いんです。
◎【足がつる=筋肉が縮っぱなしの状態!】
こむら返り(足のつり)は、ふくらはぎの筋肉=下腿三頭筋が、何らかの原因で縮んだまま戻れなくなった状態(過緊張)なのです。水分、ミネラル不足、脱水なども勿論ありますが、実は、あまり注目されていない「姿勢の乱れ」や「骨盤の歪み」も、こむら返りと深く関わっていることをご存知でしょうか?
今回は、この見落とされがちな視点から整体師としての立場でお話ししていきます。
◎【骨盤の歪みがふくらはぎにどう影響するの?】
骨盤が歪むと、全身の筋肉のバランスが崩れます。すると、ふくらはぎの筋肉にも不均衡な負荷がかかり、左右で硬さや柔軟性に差が出やすくなるんです。特に片足重心・足を組む動作・反り腰などの姿勢習慣がある方は要注意です。無意識に筋肉が緊張しっぱなしになり、寝ている間に足がつることも…
※ 『エビデンスの視点からも‼︎』
【参考】〜2018年、日本理学療法学会大会から〜
「骨盤の非対称性が、下腿三頭筋の筋緊張に影響を及ぼす可能性がある」との研究報告。
これは、骨盤の傾きが、歩行時の足への負担を変化させ、ふくらはぎの筋緊張が増すことが示唆されています。つまり、「姿勢が悪い」「骨盤がずれている」ことで、ふくらはぎの筋肉が無意識に疲労・緊張している状態が、こむら返りの土台になっているのです。
◎【DRT背骨揺らしで、こむら返りが起きなくなったケースも…】
実際に、当院に来院されている患者さまの中にも、
・以前は、頻繁に足がつっていたのにDRT背骨揺らし整体で歪みを整えたら、いつの間にかこむら返りが起きなくなっていた。という患者さまがたくさんいらっしゃいます。
これが「身体の土台を整える」ことの本当の意味なのです。単に水分を取るだけでは解決しなかった不調が、姿勢と骨格を整えるだけで、自然と起きなくなっていくのです。
◎【今回のケースは「脱水」が主因。でも…】
冒頭の患者さまの場合は、喉の痛みで数日間ほとんど水分と食事が摂れず、さらに、夜間の蒸し暑さもあり、脱水による一時的なミネラル不足が主な原因だったと考えられます。この患者さまは、施術前の検査で見ても、骨盤の歪みはなく姿勢も良好でした。つまり、普段はつることのない身体が、体調不良と急な暑さの中で、一時的にミネラル不足となり、たまたまこむら返りが起こったと考えられます。
その一方で、日常的に姿勢の崩れや骨盤の歪みがある方は、ふくらはぎの筋肉が常に緊張しやすく、こうした条件が重なったときに、より、こむら返りが起こりやすくなるのです。
つまり、
・「姿勢が整っている身体」→イレギュラーがあっても一過性。
・「姿勢が崩れている身体」→ちょっとしたことで何度も起こる。
◎【それでも、こむら返りが頻繁に続く時は…】
こむら返りが何度も繰り返される場合、中には肝臓・腎臓・糖代謝の異常等、内科的な病気が隠れていることも考えられます。このような時は病院を受診することをお勧め致します。
特に以下のような症状がある方は、一度、医療機関での検査をお勧めします。
・こむら返りが毎晩のように起こる
・疲れやすく、むくみやだるさが取れない
・黄疸や尿の色が濃くなるなど、他の変化もある
整体で改善しない不調が、実は体内の問題だったということもあるのです。まずは医療的な原因をきちんと調べる事がとても大切です。
◎【内科的な問題がなかった場合は…】
「異常なしと言われたのに、こむら返りが続く…」そんな時こそ、身体の使い方や姿勢に目を向けてみてください。骨盤や背骨の歪みが原因で、ふくらはぎに余計な負担がかかっている可能性があります。DRT背骨揺らし整体で、身体を整えることで、辛さが自然と消えた方もたくさんいらっしゃいます。
◎【まとめ: 小さなサインを見逃さないこと!】
こむら返りは「もう限界!」と身体が出しているSOSサインかもしれません。まずは医療機関でのチェックを忘れずに。そして、必要に応じてDRT背骨揺らし整体というケアの選択肢も知っておいてくださいね。
最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。感謝致します。
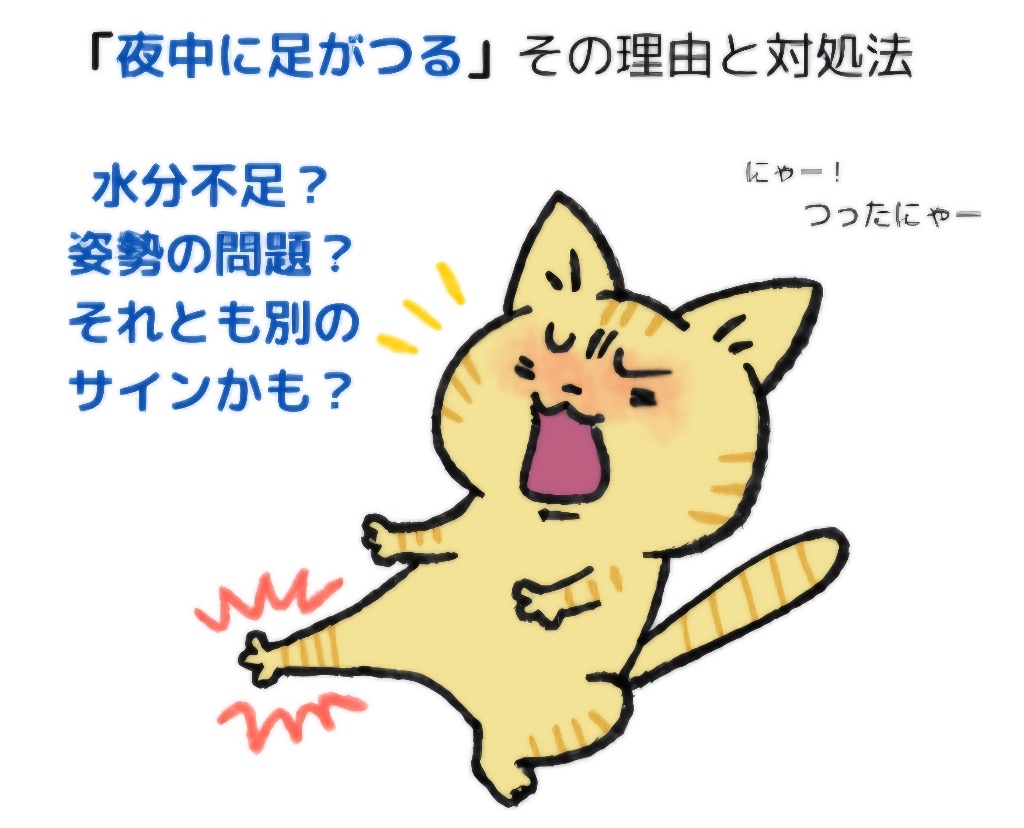
![「夜中に足がつる」その理由と対処法と⁉︎]()
2025/06/20
当院がメディアでも紹介されました‼︎
こんにちは😃
ご覧いただきまして、ありがとうございます♪
このたび、みやび整体院が6月21日付の週刊郡山ザ・ウィークリーに掲載されました。
郡山ではコンビニの数より治療院の数の方が多いと言われており、大激戦区状態と言っても過言ではありません。その中でDRT施術を行っているところは、当院のみでまだまだ知られていないのが現状です。私はこれに慢心することなく、少しでも患者さまのお力になれますよう努力して参りますので、今後ともよろしくお願い致します。

![当院がメディアでも紹介されました‼︎]()
2025/06/18
熱中症になりやすい人ってどんな人?今日からできる簡単対策!
こんにちは😃
ご覧いただきまして、ありがとうございます♪
◎【熱中症になりやすい人って?】
夏が近づいてくると、「熱中症」という言葉をよく耳にしますよね。テレビでも「こまめな水分補給を!」なんて言ってますが、「ちゃんと気をつけているのに、毎年ばてちゃう…」という人も多いのではないでしょうか?今回は、熱中症になりやすい人の特徴と、毎日できる簡単な対策をご紹介します。
◎【ちゃんと水を飲んでいるのに熱中症になる⁉︎】
・「毎日水は飲んでいるのに、午後になると身体がだるい」
・「頭がボーッとして、気分が悪い」
・「冷房の中でも、なんだか汗が止まらない」
こうした身体の不調、もしかするとそれは隠れ脱水のサインかもしれません。熱中症は外にいる時だけでなく、家の中でも起こります。実は自分では気づかないうちに身体が水分や塩分を失ってしまってるんです。
◎【真面目な人、我慢強い人ほど熱中症になりやすい?】
次のような人は熱中症になりやすい傾向があります。
・身体の声を聞かずに無理をしてしまう人
・冷房を使うのを我慢してしまう人
・年齢を重ねた人(高齢者)
・子供や小柄な人
・持病がある人や、薬を飲んでいる人
・汗をかきにくい人
つまり「我慢強い人」や「真面目な人」が気づかないうちに危険な状態になってしまうことがあるんです。
◎【解決策① : ただの水では足りない⁉︎ ミネラルと塩分がカギ!】
テレビでよく「水分補給をしよう!」と言っていますが、実はただの水ばかり飲んでいると、かえって身体の中の塩分(ナトリウム)やミネラルが薄まってしまうことがあります。これが続くと、身体のバランスが崩れて、めまいや頭痛、だるさ、痙攣などを起こすこともあります。
※ 『水分補給のオススメは?』
・白湯 : 身体を内側から温め吸収が良い
・常温の水 : 冷たすぎるとお腹に負担がかかるのでゆっくり飲もう。
・ほうじ茶 : カフェインが少なめで身体に優しい
・良い塩を少々 : 天然のミネラルが入ったお塩をひとつまみ加えると、◎
【注意!】
スポーツドリンクも良いのですが、糖分が多いので、飲み過ぎに注意しましょう‼︎
◎【解決策② : 体温調節がうまくできない? 空調を味方につけよう!】
・「冷房をつけると、寒くなるし…」
・「身体に良くない気がして…」
そんなふうに思って冷房を我慢していませんか?
実は暑さを我慢していると、自律神経が乱れて、体温調節がうまくできなくなります。するとますます汗をかけず、身体に熱がこもってしまいます。
※ 『空調の上手な使い方』
・室温は25〜28℃を目安に!
・扇風機とエアコンを一緒に使うと、空気が流れて冷えすぎ防止になります!
・外と中の温度差は、5℃以内に!
・寝る時はタイマーで自動オフ + 薄いタオルケットなどを使おう!
大切なのは「暑さを我慢しない」「冷やしすぎもしない」バランスです。
◎【熱中症は命に関わることもある‼︎】
軽いめまいや頭痛だからと放っておくと、熱中症はあっという間に命に関わる危険な状態になることもあります。
・呼びかけに応えられない
・ふらつく
・吐き気がする
・意識が朦朧とする
そんな時は、すぐに涼しい場所で休み、救急車を呼ぶことも大切です。「ちょっと変かも…」と思ったら、遠慮せずに助けを求めましょう。
◎【今日から始める3つの習慣】
☑️ 朝1番に白湯を飲もう!
寝ている間に身体はたくさん汗をかいています。コップ1杯の白湯は身体を優しく起こしてくれます。
☑️ お水にひとつまみの塩を!
天然のミネラルが入った良いお塩をちょっと加えて、水分だけでなく「ミネラル補給」も意識しましょう。
☑️ 室温チェックを日課に!
毎朝、部屋の温度を確認する習慣をつけましょう。「今日は暑くなりそうだなぁ」と思ったら、早めに空調を入れるのがお勧めです。
◎【熱中症は知っていれば防げる!】
熱中症は、水分とミネラルをしっかりとって、空調を上手に使うことで防げるものです。
・「身体がだるいのは、歳のせいかな…」
・「子供はだるそうだけど、夏だから仕方ないか…」
そんなふうに諦めずに、今日からできる対策を始めてみましょう。身体が元気になると、心も前向きになります。そして、夏の楽しい思い出をたくさん作れるようになりますよ。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。感謝致します。

![熱中症になりやすい人ってどんな人?今日からできる簡単対策!]()
2025/06/16
梅雨のだるさやイライラはタンパク質不足かも?
こんにちは😃
ご覧いただきましてありがとうございます♪
◎【梅雨の時期は憂鬱】
雨が続く梅雨の時期。「なんだか身体が重い」「気分がすっきりしない」そんなふうに感じていませんか?朝起きてもすぐに疲れたり、イライラしたり、理由もなく落ち込んでしまったり…。実はそれ「タンパク質が足りてない」ことが原因かもしれないんです。
◎【なんとなく不調…梅雨になると、毎年辛い!】
梅雨になるとこんな声を多く聞きます。
・「身体がだるくて、何もしたくない」
・「頭が重くて、集中できない」
・「朝からやる気が出ない」
・「鬱っぽくなってしまう」
・「寝ても疲れが取れない」
これらの不調は、「気象病」や「自律神経の乱れ」と呼ばれることもありますが、実はその背景に「栄養の偏り」があることに気づいていない人も多いのです。
◎【頑張っているのに不調…それは心と身体の栄養不足!】
心の元気と身体の元気はつながっています。私たちの身体は、食べたものでできています。特に脳や神経の働きに必要な「タンパク質」が足りないと、梅雨の時期の気圧の変化や天気の悪さに負けてしまいやすくなります。
・「鬱症状やだるさは、脳のエネルギー不足からくると言われています。そのためには、まずタンパク質と鉄分をしっかりとることが大切です。」
頑張り過ぎているあなた、栄養不足でエネルギー切れになっているのかもしれません。
◎【まずは、タンパク質をしっかり取ることから始めよう!】
タンパク質とは、筋肉や皮膚、髪の毛、ホルモン、免疫、そして脳の材料になる大事な栄養です。でも、現代人の食卓は「おにぎりだけ」「パンとコーヒーだけ」など、糖質ばかりでタンパク質が足りていない人が多いのです。
○ 『タンパク質を取るポイント!』
・朝食に卵、納豆、ヨーグルト、ツナ、チーズなどをプラスすればOK!
・おやつがわりに、ゆで卵やプロテイン飲料もOK!
・肉、魚、大豆を1日3回意識して食べる!
朝食にタンパク質をとると、1日のスタートがしっかり切れるので、梅雨時のリズムの乱れにも負けにくくなります。また、タンパク質を取る時は鉄分もセットで取ることがポイントです。特に女性は「隠れ鉄不足」が多く、倦怠感や情緒不安定の原因にもなります。
◎【放っておくと、夏バテ・自律神経失調症へ…】
「梅雨が過ぎれば元気になるから…」と、身体のだるさを我慢していると、そのまま夏バテや自律神経の乱れにつながってしまうこともあります。
・寝付きが悪い、朝起きられない。
・食欲がわかない。
・ちょっとのことでイライラする。
・涙が止まらない、気持ちが不安定。
そんな状態が続くと、心のエネルギーも底ををつき、「何もしたくない」「動けない」なんてことにもなりかねません。今のうちに自分の栄養を見直すチャンスと考えて、心と身体の土台を整えておきましょう。
◎【今日からできる3つの習慣】
難しいことを始めなくても、まずは「できることから」でOK。
1.『朝食に卵や納豆をプラスしよう』
「パンだけ」「コーヒーだけ」では、エネルギーが足りません。卵一個と納豆だけでも朝のやる気が全然違います。
◎【プロテインを取り入れてみる】
食べるのが難しい時は、プロテイン飲料でもOK。
子供も飲めるタイプがあるので、家族みんなで取り入れてみましょう。
3.『よく噛んで食べる』
栄養は、よく噛んで消化してこそ吸収されます。食べる時はスマホを置いて、ゆっくりと食事を楽しみましょう。
◎【ちゃんと食べればちゃんと元気になる?】
「最近なんかしんどいなぁ…」と思っていたら、それはあなたが悪いわけではなく、栄養が足りていないだけかもしれません。私たちの身体は、きちんと食べて、よく寝ればちゃんと元気を取り戻します。梅雨が明けたら、夏の太陽が待っています。その時に思いっきり動けるように、今から身体のエネルギーをしっかり貯めておきましょう。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。感謝致します。
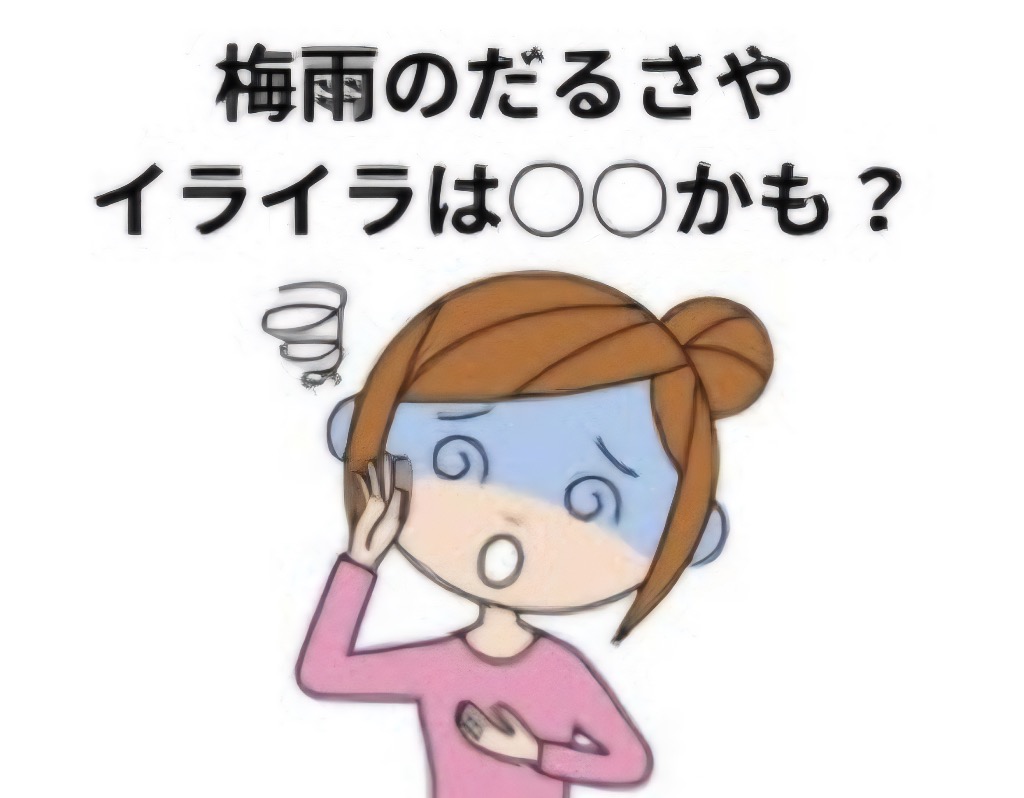
![梅雨のだるさやイライラはタンパク質不足かも?]()
2025/06/14
ストレッチで五十肩を予防しよう!
こんにちは😃
ご覧いただきまして、ありがとうございます♪
◎【よくある声】
・「肩が急に上がらなくなった」
・「腕を後ろに回すと痛い…」
・「服を着るのも一苦労…」
そんな声をよく聞きます。これは「五十肩」と言われる肩関節の不調です。でも、もし毎日の習慣で防げるとしたらどうでしょうか?今回は家でできるストレッチで五十肩を防ぐコツをお伝え致します。
◎【気づいたら肩が動かない…】
五十肩は、「肩関節周囲炎」という正式な病名があります。その名の通り、肩の関節の周りに炎症が起きて動かしづらくなるのが特徴です。
○よくある症状は…⁉︎
・洗濯物を干す時、肩が上がらない
・洋服を着たり脱いだりするときに痛い
・夜寝ていると肩がズキズキする
・髪をとかす動作が辛い
これらの辛さは、ある日いきなりやってくることが多いのです。
◎【何故か片方だけ…日常に潜む落とし穴⁉︎】
・「右手ばかりで、荷物を持っていた」
・「スマホばかり見ていて、姿勢が悪くなっていた」
・「寒い時期は肩をすくめたまま、じっとしていた」
こんな日々の小さな積み重ねが、知らないうちに肩に負担をかけてしまっていたのです。そしてある日、「何か変だな…」と気づいた時には、もう痛みが出ているなんてこともありますよね!
「これは、どうせ歳のせいでしょう?」そんな声も聞こえてきますが、予防できることもたくさんあるんです!
◎【ストレッチで「動く肩」をキープ!】
五十肩の予防には、肩周りの血流を良くすること、そして関節の可動域(動かせる範囲)を保つことがとても大切です。そのためには「ストレッチ」が効果的です。ストレッチといっても難しい事はありません。毎日ほんの数分だけゆっくり動かせばいいんです。
◎【放っておくと、動かなくなることも…】
肩は動かさないと固まるという少し厄介な場所です。五十肩になると『腕が上がらない、後に回せない、痛みが長引く』などの症状が出て、酷い場合は1〜2年治らないこともあります。
「痛いから動かさないでおこう」と思っていると、ますます筋肉が硬くなり、凍結肩(とうけつかた)という状態になってしまうこともあります。そうならないように、今から肩をいたわることがとても大事です。
◎【今日からできる五十肩予防、ストレッチ3つ!】
1.『タオルストレッチ』
・タオルの両端を持って頭の上でぴんと張ります。
・息を吐きながら、タオルをゆっくり後ろに引きます。
・息を吸いながら、元の位置に戻します。
○ ポイント
その1…肩甲骨を意識して動かすと効果的です。
その2… 10回を目安にゆっくり動かそう。
2.『壁のぞきストレッチ』
・両手を壁に当てて身体を少し前に倒します。
・肩甲骨を寄せるようにして肩を伸ばします。
○ ポイント
その1…痛くない範囲で深呼吸しながら行う。
その2…10〜15秒キープして3セット行う。
3.『ペットボトルぶらぶら運動』
・水を入れたペットボトルを片手に持ち前かがみになります。
・肩の力を抜いてペットボトルを前後にゆらゆら動かします。
○ ポイント
その1…力を入れず、重力に任せて揺らすイメージです。
その2…左右それぞれ30秒ずつ行う。
◎【毎日の小さな積み重ねが、大きな違いに‼︎】
五十肩は、ある日突然やってくるように見えて、実は日ごろの身体の使い方が深く関係しています。だからこそ、今日からちょっとずつ気をつけることが、未来の元気な身体を作る第一歩です。
・姿勢を正す
・肩をゆっくり回す
・ストレッチを続ける
・無理をしない
これだけでも五十肩のリスクをぐっと減らすことができます。
・「最近なんだか肩が軽くなったかも…?」
・「この前より腕が動いている気がする」
・「肩の痛みが軽減しているかも…?」
とそんなふうに感じられたら、あなたの身体は少しずつ変わっている証拠です。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。感謝致します。
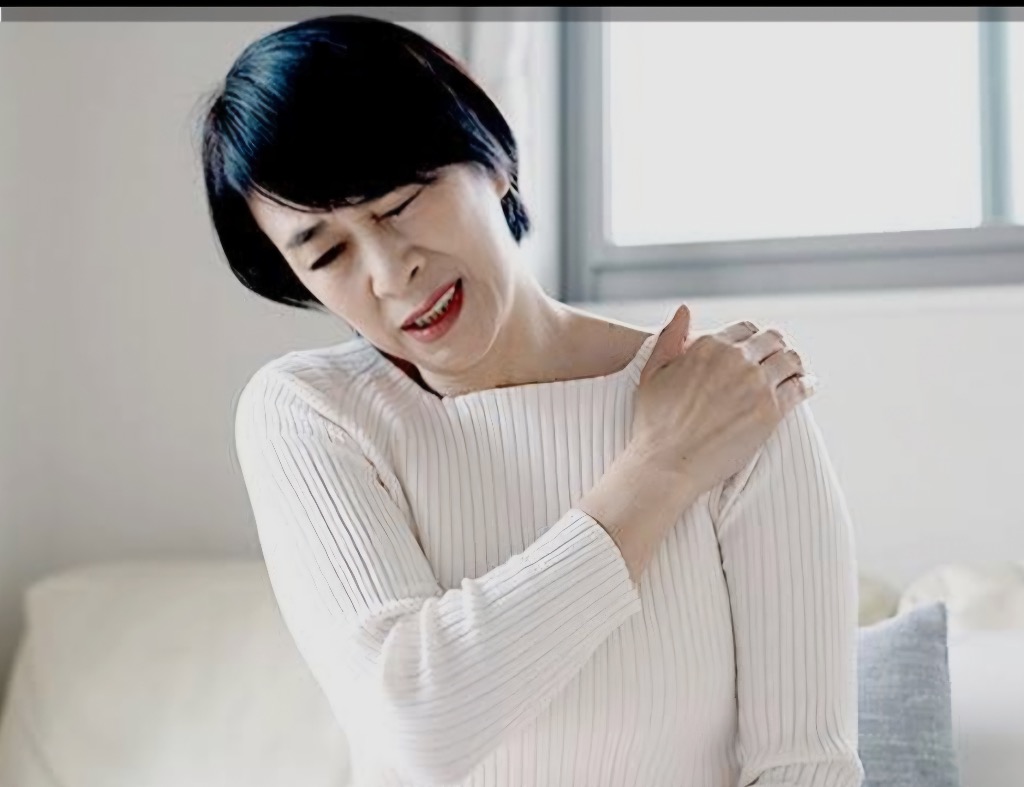
![ストレッチで五十肩を予防しよう!]()