2025/06/08
冷房に負ける・手足が冷たい・なんとなく不調…
こんにちは😃
ご覧いただきまして、ありがとうございます♪
◎【それ、冷えが原因かもしれません⁉︎】
6月に入り、街ではノースリーブやサンダルなど、軽やかな装いの女性たちを多く見かけるようになりました。でも、ふと患者さんに手を触れた時、毎年この時期、その冷たさに、はっとさせられます。「こんなに暑いのに、どうしてこんなに手足が冷たいの…?」そしてもう一つ、この時期に増えるのが「冷房が苦手」「クーラーに当たると体調が悪くなる」という声です。
実は、この真夏の寒がりこそ、見逃されがちな「冷え性」のサインなのです。しかも、本人は「暑がりだと思っていた」「冷えているなんて思ってもいなかった」と自覚症状がないことが多いのです。そんな女性たちが身体からの声に、もっと耳を傾けてほしいとそう感じた私は改めて「冷え」について掘り下げていこうと思います。
◎【気づけていない「冷え」というサイン!】
当院では、患者さまの来院時に手指の消毒と検温を毎回させていただいています。この暑い時期、特に女性患者さまで平熱が35度台という方が多く見受けられます。平熱がもともと低い体質だと思われがちですが、そこに大きな落とし穴があります。
実はそれ「自然治癒力が働かない状態」になっている身体からのSOSサインなのです。
◎【「冷え」は病気じゃない!でも放っておくと…】
西洋医学では、「冷え性」は病名ではありません。検査では異常がない。でも、体調はなんとなく悪い。そういった不調が続くのは「冷え」の怖さです。体温が下がると、血流が悪くなり、免疫力や代謝が低下します。その結果、肩こり・腰痛・不眠・生理不順・便秘・疲れやすさなど、様々な不調が起こるようになります。例えば、体温が1℃下がると免疫力は約30%低下すると言われています。また、血流が悪い箇所にはがん細胞ができやすいとも言われており、体温が36.5℃以上でないとがん細胞が死滅しにくいという研究もあり、「冷え」は未病ではあっても、決して軽く見てはいけないものなのです。
◎【冷えの原因は、生活の中にある!】
冷えを引き起こす原因は大きく分けて3つあります。
1.『血流の悪化』
・姿勢の崩れ、運動不足、ストレスなどで血液循環が悪くなります。
2.『筋肉量の低下』
・筋肉は熱を生み出すエンジンです。女性はもともと筋肉が少なく、冷えやすい体質なのです。
3.『自律神経の乱れ』
・ストレスや冷房、睡眠不足などで自律神経が乱れると、体温調節がうまくいかなくなります。さらに、こうした要因が重なることで、手足だけでなく、お腹や内臓までも冷えてしまう「内臓冷え」につながることもあります。
◎【「冷え」に気づけることが第一歩!】
・「自分は暑がりだから、冷え性じゃないと思っていた」
・「なんとなく疲れやすいのは、年齢のせいだと思っていた」
そんな声を整体の現場では本当に多く耳にします。
※ 『背骨のバランスが整うと、自律神経のバランスと自然治癒力がUPします‼︎』
それに気づけた今こそ、整えるチャンスです。当院では、背骨を優しく揺らしながら、歪みを整える「DRT背骨揺らし施術」で、自律神経の働きを整え、血流や代謝をアップさせ、自然治癒力を引き出す施術をしています。施術後には冷えに悩んでいた方が「なんだか身体全体がポカポカしてきた」「最近、夜眠れるようになった」等、小さな変化から自分の身体と向き合い始めています。
◎【冷えは我慢するものじゃない!】
「冷え性」は体質でも年齢のせいでもありません。身体は正しく整えてあげれば、必ず応えてくれます。まずは「もしかして冷えてるかも?」に気づくこと。それが「冷えからの卒業への第一歩」です。「なんとなく不調かも…?」その原因は、もしかしたら「冷え」かもしれません。そう気づいた今が整えるタイミングなのです。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。感謝致します。
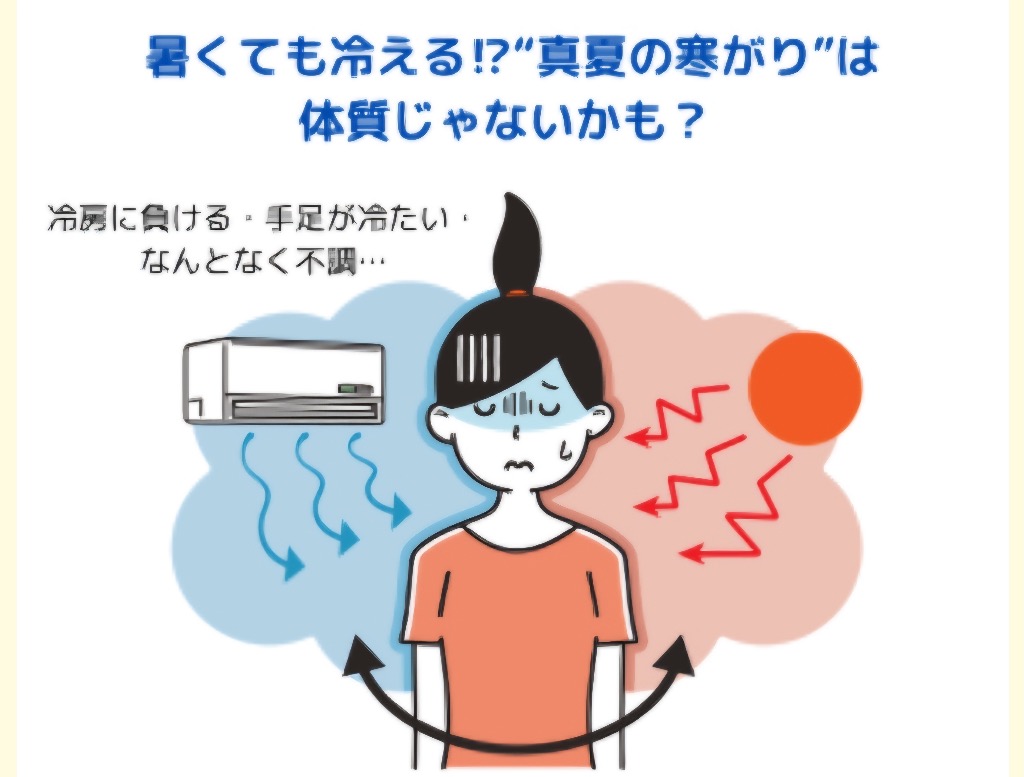
![冷房に負ける・手足が冷たい・なんとなく不調…]()
2025/06/06
雨の日にオススメ!気分が上がるおうち時間のコツ⁉︎
こんにちは😃
ご覧いただきまして、ありがとうございます♪
◎【お家の中でも心は晴れやかに】
・「雨が続いてなんだか元気が出ない」
・「家の中ばかりでつまらない」
・「やることがないし、眠いし、イライラする…」
そんなふうに感じている人、きっとたくさんいますよね。実はそれ、雨の日に心と身体のバランスが崩れてしまっているからかもしれません。でも大丈夫。ちょっとした工夫で、雨の日のおうち時間も楽しくなります!
◎【雨の日が続くと、なんだか調子が悪い…】
雨が降ると、外に出るのが面倒になったり、空が暗くて気持ちもどんよりしてきたりします。また、気圧が下がることで、自律神経が乱れやすくなり、次のようなことが起こりがちです。
・頭が重い、身体がだるい
・眠たいのに寝てもスッキリしない
・イライラする、集中できない
・なんとなくやる気が出ない
これは、光を浴びる時間が減ったり、生活リズムが崩れることで、「セロトニン」という気分を明るくするホルモンが少なくなってしまうのも関係しています。
◎【家にこもると、余計にモヤモヤ…】
・「家にいても、なんだかつまらない」
・「Netflix、YouTube、スマホやテレビばかりで、逆に疲れる」
・「大人も子供もストレスが溜まりがち」
そんな日が続くと、心も身体もモヤモヤしたままになりますよね。特に梅雨などで雨が続く時期には、おうちの中でいかに気分転換するかがとても大事になります。
◎【心と身体をリセットする「おうちリズム」を作ろう!】
雨の日でも、楽しく元気に過ごすためには「生活リズム」と「ちょっとした楽しみ」がポイントです!
1.『朝はカーテンを開けて光を取り込もう』
・どんなに空が暗くても、外の光を浴びる事はとても大切です。自律神経のリズムが整い、体内時計が正しく働くようになります。
・朝の5分、窓を開けて深呼吸するのも効果的です!
2.『ご飯で元気チャージ!』
・心と身体を元気にするためには、朝ごはんや昼ご飯をちゃんと食べることも大切です。あったかいスープやご飯、お味噌汁など、身体を温めるメニューがお勧めです。
・食事の時間は、心のリズムも整える大切な時間です!
3.『おうちでミニイベントを開こう!』
・雨の日のおうち時間がマンネリにならないように「お楽しみ時間」を作ってみましょう。
例えば、
・おうちカフェ(好きな飲み物と、おやつでゆったりする)
・プチ読書タイム(好きな本を10分間だけ)
・家族でストレッチやヨガ(YouTubeでもOK)
・雨音を聞きながら趣味を楽しむ
・自分だけのひとり時間もあり!
「今日は何をしよう?」とワクワクすることを1つ決めるだけでも違います。
4.『身体を緩める「お風呂リズム」』
・冷えた身体を温めると、心もリラックスしやすくなります。ぬるめのお風呂にゆっくりつかって、身体も気分もリセットしましょう。
・お気に入りの入浴剤や、優しい音楽を流すともっと心地良いですよ!
◎【リズムが崩れると、心にも身体にも悪いことが…】
「だるい」「イライラする」「なんとなく元気がない」そんな日が続くと、自分でも気づかないうちにストレスが溜まっていきます。
・寝付きが悪くなる
・体調を崩しやすくなる
・気分が落ち込んでしまう
雨の日が原因でこうなってしまうのは、とてももったいないこと。だからこそ、雨の日こそ意識して「楽しいリズム」を作ることが大切なんです。
◎【小さなひと工夫で変わるおうち時間!】
では、今日からできることをまとめてみましょう。
・朝カーテンを開ける
・ご飯をしっかり食べる
・1つ「楽しいこと」を決めてみる
・身体を動かしてみる(3分でもOK)
・ゆっくりお風呂につかる
この中から1つでもやってみることが「雨の日の自分を守る第一歩」になります。
◎【まとめ】
・「雨の日でも、今日はちょっといい感じ」
・「楽しそうに過ごせる」
・「イライラが少なくなった」
そんなふうに思える日が、少しずつ増えていくはずです。お天気は選べません。でも、どう過ごすかは自分で選べます。自分の心と身体に優しく向き合いながら、雨の日だからこそできる「ゆったりリズム」を楽しんでいきましょう。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。感謝致します。

![雨の日にオススメ!気分が上がるおうち時間のコツ⁉︎]()
2025/06/04
朝の光と心の健康
こんにちは😃
ご覧いただきまして、ありがとうございます♪
◎【目覚めが変われば1日が変わる⁉︎】
・「朝、起きても、なんだかスッキリしない…」
・「イライラしたり、気持ちがモヤモヤする…」
そんなふうに感じたことがありませんか?
実は、その原因「朝の光」にあるかもしれません。
◎【朝の光ってそんなに大事なの?】
はい、すご〜く大事なんです!!!
私たちの身体には「体内時計」というものがあります。これは朝起きて、夜に寝るというリズムを作る時計のようなものです。この体内時計を正しく動かすために、一番必要なのは「朝の光」なんです!
◎【うちの子も朝が苦手で…そんな声がたくさん】
・「朝になっても、家の子が起きてこない」
・「会社や、学校に行くのが辛い」
・「機嫌が悪くて、朝から喧嘩になる」
そんな声が、いろんなご家庭から聞こえてきます。実は、朝が辛くなるのは、心のせいだけじゃありません。生活リズムの乱れが原因で、自律神経やホルモンバランスが崩れてしまうことがあるんです。
◎【自律神経とセロトニンって何?】
朝の光を浴びると、脳の中で「セロトニン」というホルモンが作られます。これは「幸せホルモン」とも呼ばれていて、心を落ち着かせたり、元気を出したりする働きがあります。また、自律神経も朝の光でリセットされます。これがうまく働くとやる気が出たり、気持ちが前向きになったりするんです。
◎【朝の光を浴びないとどうなるの?】
・イライラする
・いつまでも眠い
・やる気が出ない
・昼夜逆転になる
・心の元気がなくなる(鬱状態に近づく)
こんなふうに、心と身体のバランスが崩れてしまいます。特に、梅雨の季節や冬は日照時間が少なくなるため、気分の落ち込みや自律神経失調症になりやすいと言われています。
◎【朝の光を味方につけよう!】
それでは、どうすれば朝の光の力をうまく使うことができるのでしょうか?
ポイントはたったの3つです。
1.『カーテンを開けるだけでOK !』
朝起きたら、まずカーテンを開けて太陽の光を浴びましょう。曇りの日でも、外の光は電気より何倍も明るいんです。
2.『少しだけでも外に出てみよう!』
朝、5〜10分で良いので、バルコニーや玄関先に出てみるのも効果的です。また、犬の散歩や、ゴミ出しのついでにできたらバッチリですね。
3.『朝ご飯をしっかり食べよう!』
朝の光と朝食のダブル効果で、体内時計はもっと元気に働き出します。パンでもおにぎりでもOK!「食べる」ことで、脳にもスイッチが入ります。
◎【「朝のダラダラ」が将来のリスクに?】
「まぁ、ちょっと朝ゆっくりでも…」と思っていても、そのまま何ヶ月も続いてしまうと、生活リズムが完全に崩れてしまうこともあります。
○特に怖いのは、
・出社できない、不登校や遅刻が続く
・気分の落ち込みが強くなる
・自律神経が乱れてずっと体調が悪い
等、心と身体の問題がどんどん広がってしまうことです。大人も子供も、リズムが乱れると本当に辛くなるのです。
◎【まずは「朝のカーテン開け」から!】
「何をすればいいのかわからない…」という人も大丈夫です。まずは、朝起きてすぐカーテンを開けることから始めてみましょう。それだけで、脳と身体が「朝だ!」と気づき、セロトニンが出て気分がゆっくり上がっていきます。
○さらに余裕があれば、
・外に出て深呼吸する
・ストレッチする
・「おはよう」と声を出して挨拶する
こんなことも加えるとより効果的ですよ。
◎【朝の光で、心もピカピカに!】
朝の光は、無料で使える心と身体の薬です。
・カーテンを開けるだけで、
・ちょっと元気になって、
・ちょっと優しくなれて、
毎日が少しずつ変わっていきます。
・「最近朝が楽しみになってきたかも…」
・「なんだか、気持ちが明るくなった気がする」
そんな声が、あなたやあなたの大切な人から聞こえてくるかもしれません。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。感謝致します。

![朝の光と心の健康]()
2025/05/28
目の疲れと、睡眠の関係について⁉︎
こんにちは😃
ご覧いただきまして、ありがとうございます♪
◎【夜ぐっすり眠れたら朝スッキリ見える?】
最近こんな事はありませんか?
・朝起きても目がパッチリしない
・スマホやゲームの後、目がしょぼしょぼする
・目の奥がズーンと重たい
・昼間なのに、なんだか眠たい…
等、実はこれ「目の疲れ」と「睡眠の質」が関係しているんです。私たちの身体は目から入ってくる光で「昼」や「夜」を判断して、体内時計を調整しています。でも、現代の生活は、スマホやテレビ等からのブルーライトでこのリズムが狂ってしまいがちです。
◎【目の疲れが睡眠の邪魔をする?】
目が疲れると「目のかすみ」や「ドライアイ」だけでなく、頭や肩まで重く感じたりします。これが夜になっても続くと、身体がリラックスモードに入れなくなってしまうのです。
人の身体には「交感神経」と「副交感神経」という自律神経があります。
・日中に頑張る神経 (交感神経)
・夜にリラックスする神経 (副交感神経)
目が疲れたままだと、交感神経がずっとON のままに…。すると、夜になっても心も身体も休まらずに、眠りが浅くなってしまいます。
◎【よく寝たはずなのに、目がすっきりしない理由】
「8時間も寝たのに、まだ眠い…」という人もいますよね。これは睡眠の質が悪いせいかもしれません。質の良い睡眠には、こんな条件が必要です。
・寝る前に目や脳がちゃんとリラックスしていること
・身体が冷えすぎたり、暑すぎたりしていないこと
・寝る前にスマホやテレビを見すぎていないこと
もし、寝る直前までブルーライトを浴びていたり、目がしょぼしょぼのままだと、深い眠り(ノンレム睡眠)に入るのが難しくなります。
◎【このまま放っておくとどうなるの?】
目の疲れと睡眠不足をずっと放っておくと…⁉︎
・集中力が落ちる
・イライラしやすくなる
・朝が辛くて、学校に行きたくなくなる
・頭痛やめまいが出る
・自律神経のバランスが崩れる
等、さらに酷くなると「睡眠障害」や「自律神経失調症」につながることもあります。
「ちょっと疲れているだけ…」と思っていても、身体の中では大きな変化が起きているかもしれません。
◎【じゃあどうすればいいの?】
ここからは、目の疲れを癒し、ぐっすり眠るための方法をご紹介します。
1.『ブルーライトカットを意識する』
寝る1時間前には、スマホ・ゲーム・テレビはできるだけお休みする。どうしても見たい時は、画面の「ブルーライトカット」モードを使うか、「ブルーライトカットメガネ」を使うと良いですよ。
2.『目を温めてから眠る』
目が疲れている時は、温めるのが効果的です。
(やり方は、超簡単!!)
1. 清潔なタオルを濡らして、レンジで30秒から1分ほどチンする。
2. それを目の上に乗せて、3〜5分リラックスするだけ!
たったこれだけで、目の周りの血流が良くなって、交感神経がOFF になり、ぐっすり眠りやすくなります。
3.『寝る前の光・音・臭いに気をつける!』
・照明は暗めに! (電球色の明かりがオススメです)
・静かな音楽や自然の音を流すと、◎
・ラベンダー等のアロマもリラックスするのに効果的!
五感(視覚・聴覚・嗅覚)から副交感神経を優しく刺激することで、目も心もリラックスしていきます。
4.『目を使わない(眠りのスイッチ)を作る』
スマホの代わりに…
・絵本や紙の本をゆっくり読む
・深呼吸を5回ぐらいしてみる
・ストレッチをして、首や肩を緩める
これらは、目を使いすぎないでできる「眠りの準備」なのです。夜がグンと楽になりますよ。
◎【今日からできる小さな一歩】
「全部やるのは難しい…」と思ったら、一つずつ始めてみましょう。例えば「寝る前の10分だけスマホを見ない」でもOK! それだけでも目は「ありがとう」と言ってくれますよ。
◎【まとめ】
目が疲れると、心も身体もどんよりしてしまいます。でも、ぐっすり眠ってちゃんと目が回復すれば…
・朝の光がまぶしくて気持ちいい
・勉強や仕事に集中できる
・表情が生き生きして周りにも優しくなれる
そんな毎日があなたを待っていますよ!!!
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。感謝致します。
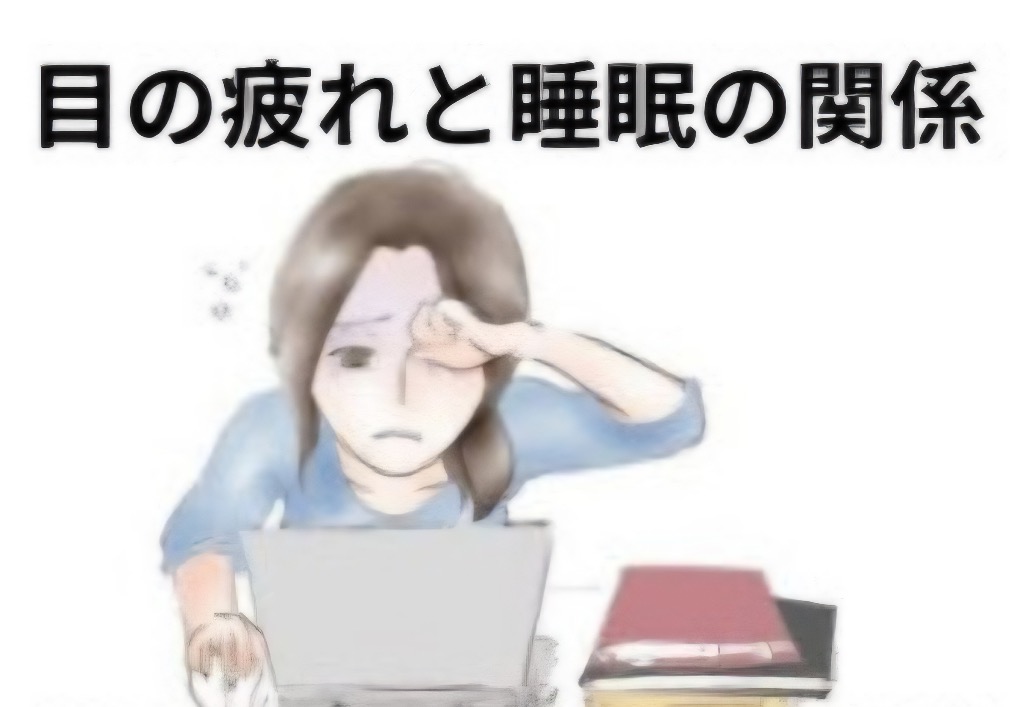
![目の疲れと、睡眠の関係について⁉︎]()
2025/05/26
ストレスと耳鳴りのつながり⁉︎
こんにちは😃
ご覧いただきまして、ありがとうございます♪
◎【聞こえないはずの音が聞こえるのはなぜ?】
夜、布団に入った時、静かな場所で集中しているときに「キーン」「ジーッ」「ピーッ」という音がしているような気がする…。でも周りは静か、テレビもラジオもついていない。この音はどこから聞こえているのだろう?実はそれ、耳鳴りという身体からのSOSサインかもしれません。
◎【耳鳴りって何?】
耳鳴りとは、「実際には音がないのに、何か聞こえるような感じ」のことです。「キーン」「ジーッ」「ボーッ」等、人によって聞こえ方は様々です。耳が悪くなったから起こると思われがちですが、耳そのものではなく、脳や神経の問題が関係していることもあります。
◎【ストレスと耳鳴りの関係って?】
私たちの身体には、「自律神経」という身体を調整する大事な仕組みがあります。この自律神経には2つの役割があります。
・活動モードの「交感神経」
・リラックスモードの「副交感神経」
ストレスが溜まると、「交感神経」がずっと頑張りすぎてしまいます。そうなると、耳の中の血流が悪くなったり、音を感じる神経が敏感になったりして、耳鳴りが起こるのです。
◎【どんなストレスが耳鳴りを引き起こすのか?】
・学校や仕事での緊張
・人間関係での気疲れ
・寝不足や不眠
・運動不足やスマホの見すぎ
・音に敏感になっている時
こんな日が続くと、心と身体がピリピリして、小さな音にも神経が反応しやすくなってしまうのです。
◎【放っておくとどうなるの?】
・「ちょっと気になるだけだし、そのうち消えるかも?」
と思って、そのままにしておくと…
・寝付けない、途中で目が覚める
・音が気になって集中できない
・いつもイライラする
・胃が痛くなったり、頭痛が出たりする
等、ストレスからくる体調不良がどんどん増えてしまうこともあります。
※耳鳴りの種類にも目を向け、耳を傾けましょう!
【耳鳴りの原因】
・ジージー(虫の音)→ 老化
・キーン→ ストレス
・ヒューヒュー→ OA機器症候群
・ウォンウォン(モーター音)→ 自律神経
・ミーンミーン→ 中耳炎
・ゴー(ジェット音)→ 脳梗塞
・グァングァン(洗濯機)→ 脳卒中
◎【今日からできる耳鳴り、ストレスの和らげ方】
1.『呼吸をゆっくりしてみよう』
・緊張した時、呼吸は早くて浅くなりがちです。お腹を膨らませながら「スーッ、ハーッ」とゆっくり深呼吸をすると、副交感神経が働いてリラックスできます。
2.『夜のスマホは、早めにおしまい!』
・寝る前までスマホやゲームをしていると、脳がずっと活動モードのままで眠りが浅くなります。寝る1時間前にはスマホを止めて、目や耳を休ませましょう。
3.『耳周りの血流を良くする』
・耳鳴りは、耳への血流がカギです。タオルを温めて耳の後ろに当てたり、耳たぶをぐるぐる回したりすることで、内耳が柔らかくなります。
4.『静かな時間を怖がらない!』
・音が気になると「静けさ」そのものが怖く感じることもあります。でも、静かな時間に心を緩めるトレーニングをすることで、少しずつ音への過敏さも減っていきます。
◎【耳鳴りに効く、簡単なツボ3つ!】
・翳風(えいふう)→ 耳たぶの後ろの凹み(血流アップ)
・完骨(かんこつ)→ 耳の後、首の付け根(緊張ほぐし)
・神門(しんもん)→ 手首の小指側の凹み(リラックス)
これらを優しく指で3秒押してゆっくり離す。これを3回ずつ行う。毎日の習慣にすると、少しずつ身体も落ち着いていきますよ。
◎【小さな事でも、毎日続けることが大事!】
耳鳴りは、我慢強い人に多いと言われます。
・「自分が頑張ればいいんだ」
・「周りに迷惑をかけたくないんだ」
そんな気持ちはとても素晴らしいことですが、自分の身体のSOSサインを無視しないことがとても大事です。
・辛いと思ったら休むこと
・誰かに話すと楽になる
・外に出て深呼吸をする
それだけでも自律神経は少しずつ整っていきます。
◎【まとめ】
耳鳴りがあると、静かな時間が怖くなります。でも、心と身体が整ってくると、その静けさが「安心」に変わる日が必ずやって来ます。今日できることを一つでもやってみる。それが明日、そして1ヵ月後のあなたを守りますよ。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。感謝致します。
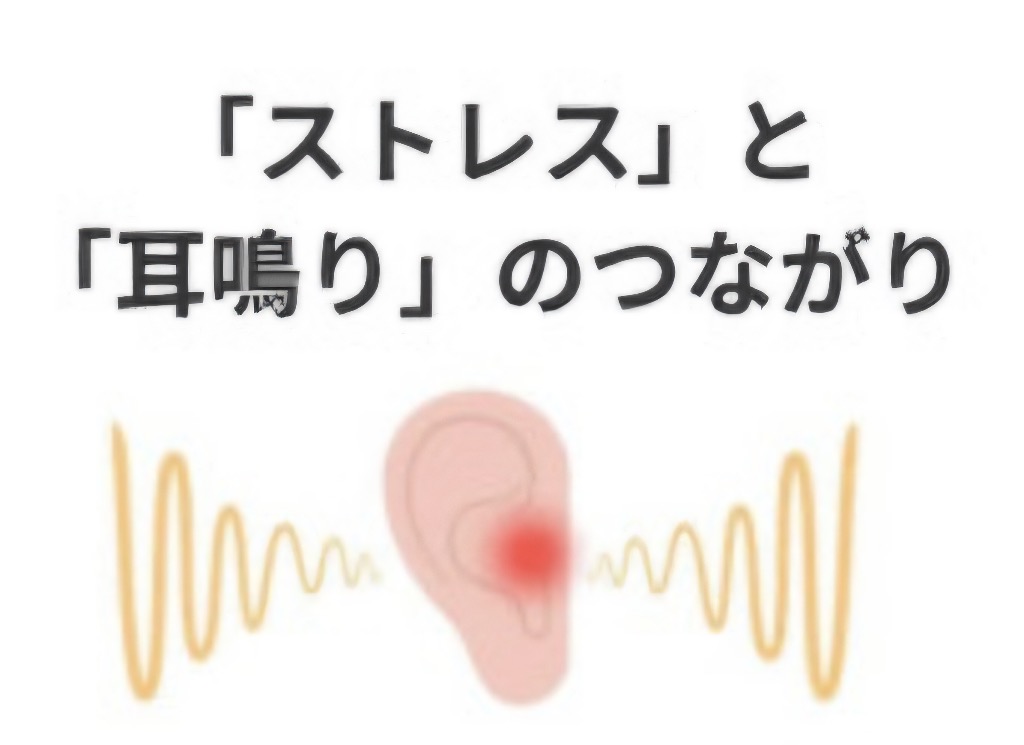
![ストレスと耳鳴りのつながり⁉︎]()